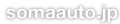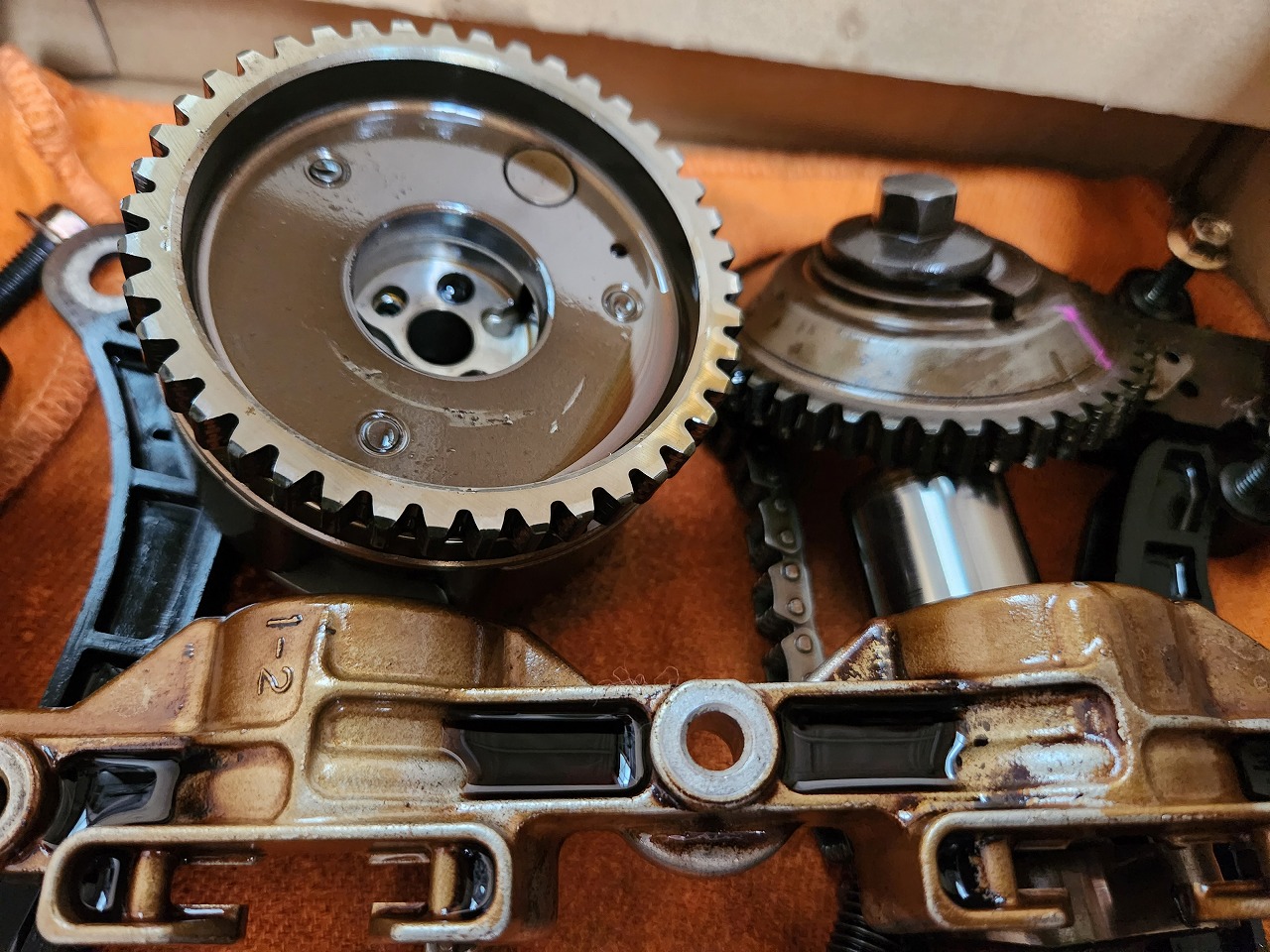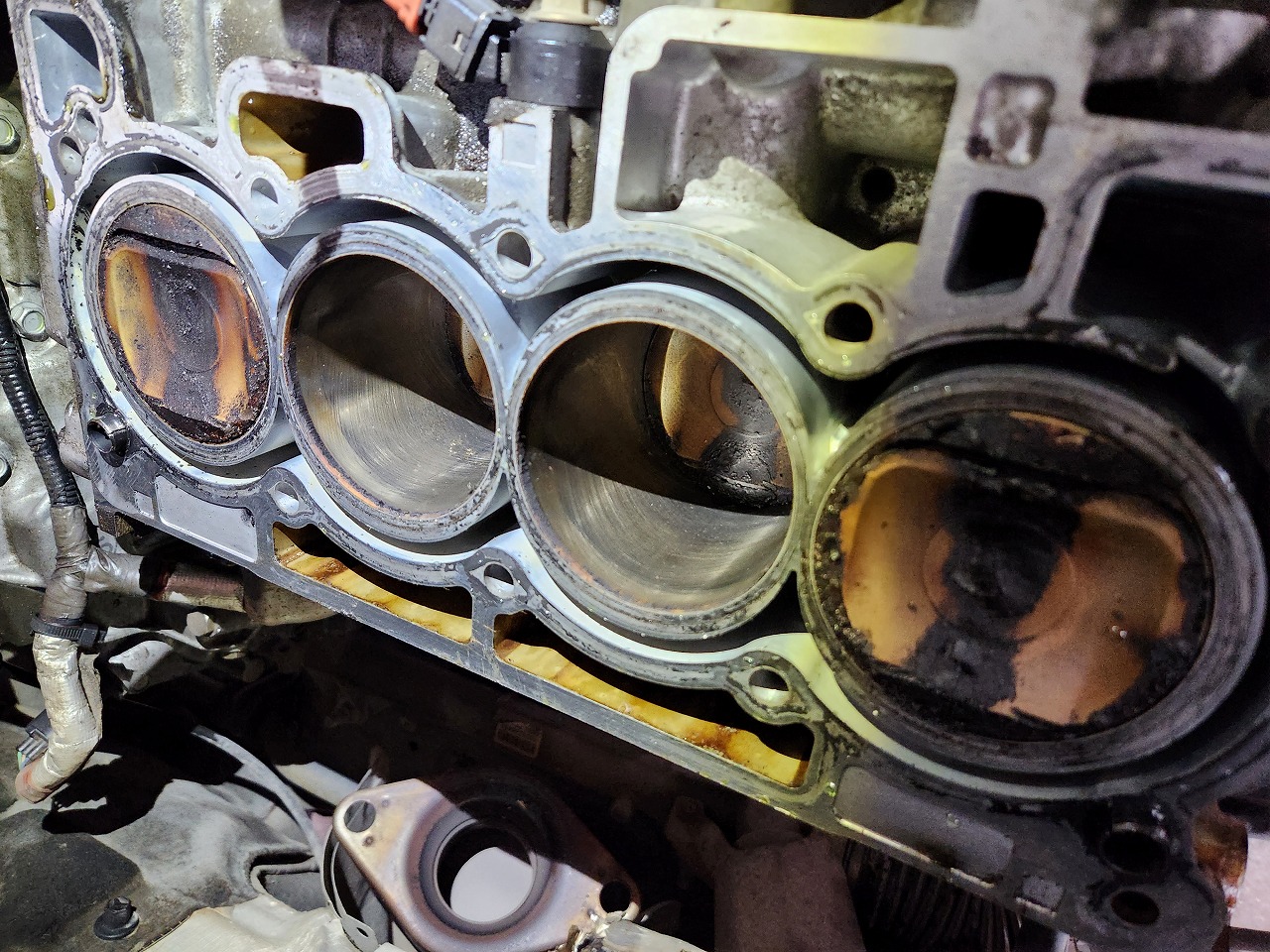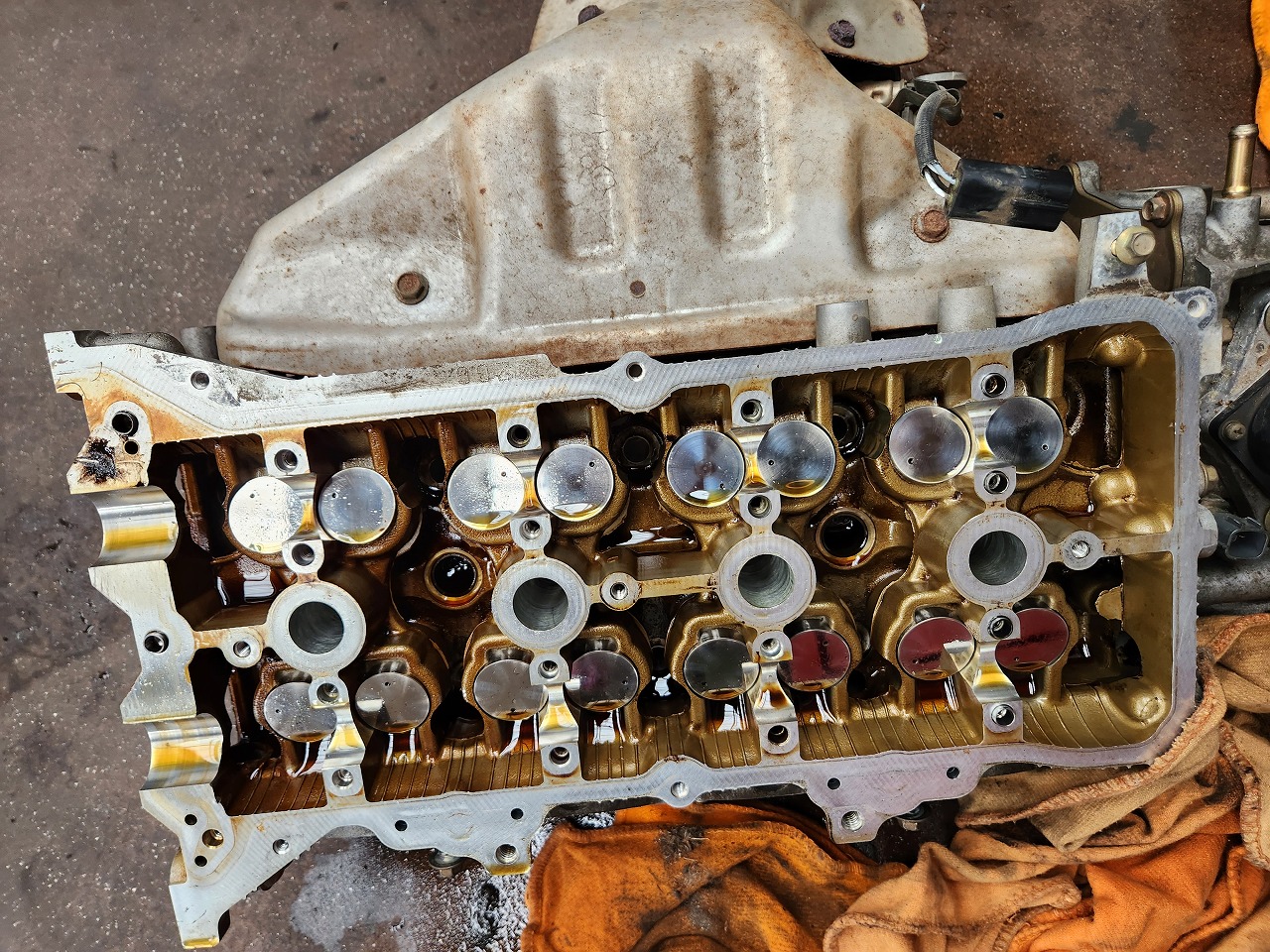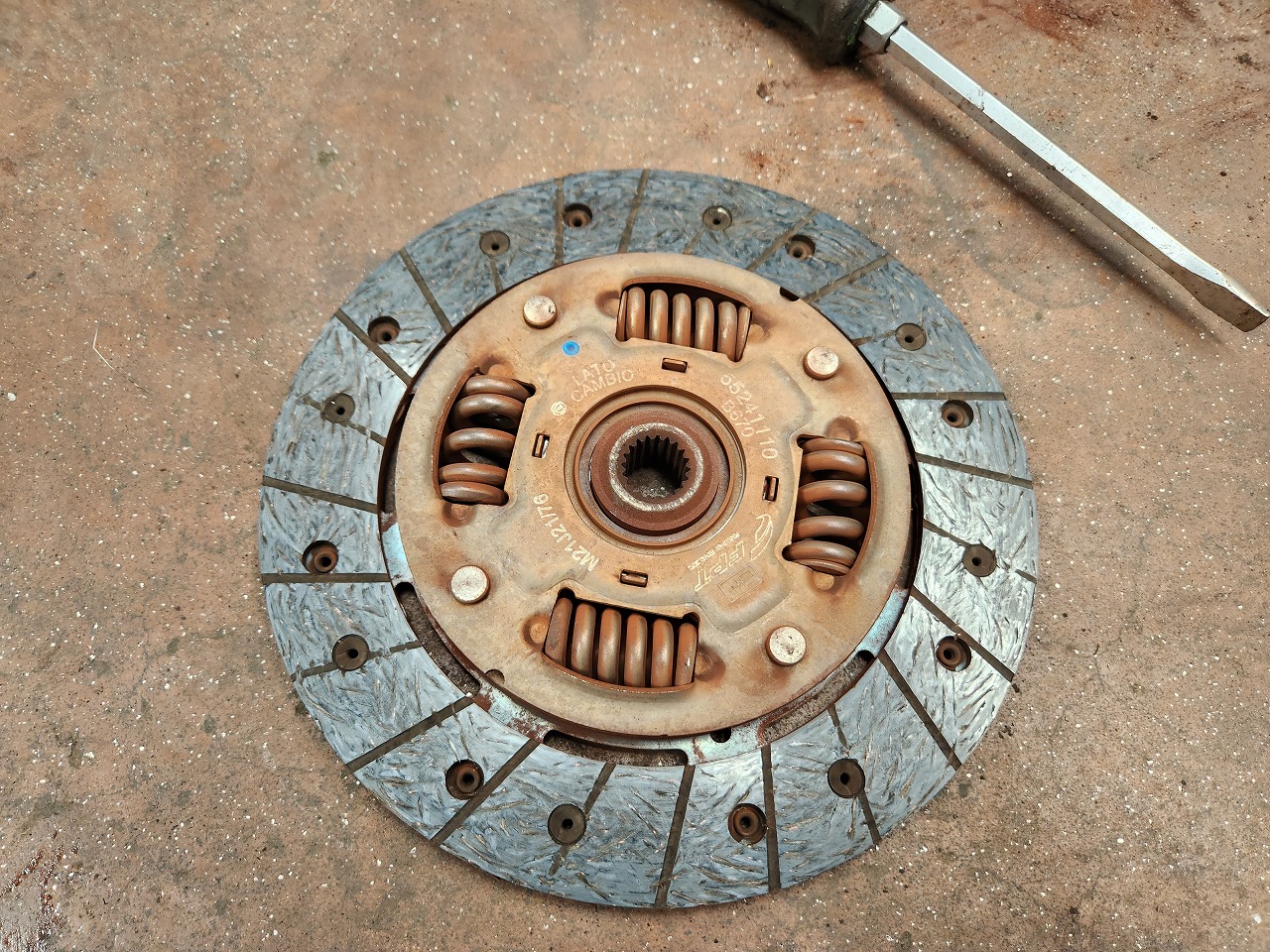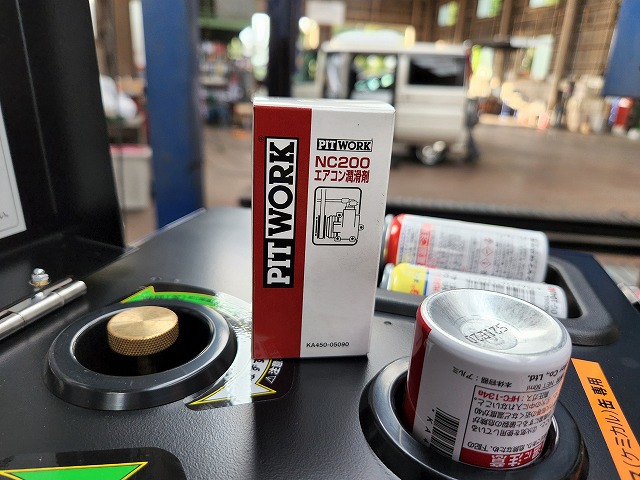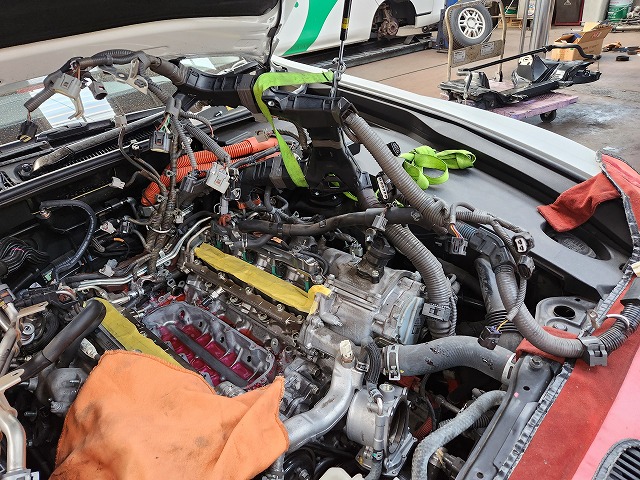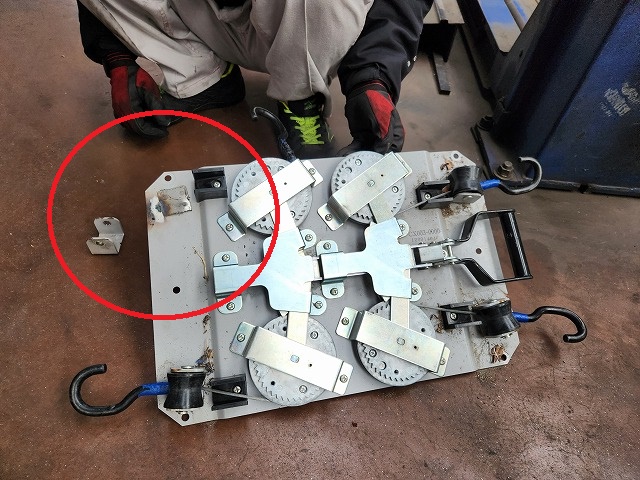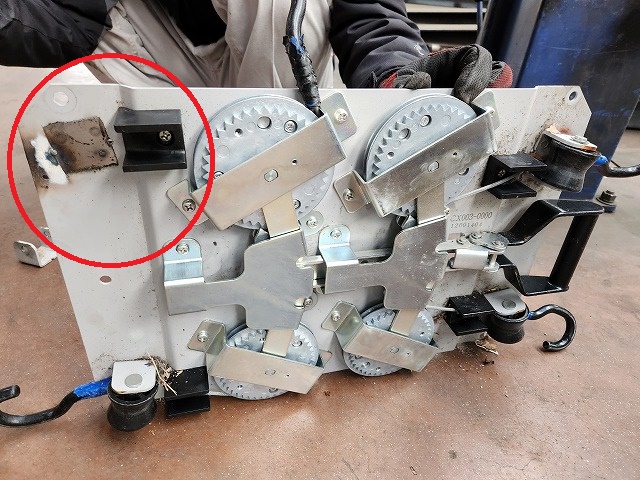トルコン太郎のイメージビデオ。
●2024.02.07
当社の主力機器のトルコン太郎。
圧送方式で過走行のお車でもオートマオイル交換オッケー。
とか言ってもなかなかイメージしづらいと思いますので
実際の作業を撮影してまいりました。
面白がって動画でアップしますので”あ、こういうことね”とか
圧送方式によるオートマCVTオイル交換をイメージしていただけたら嬉しいです。
トルコン太郎によるオートマオイル交換をご希望のお客様、
説明だけでも聞いてみたいお客様、
お見積ご希望のお客様、どうぞお気軽にお問い合わせください。
整備スタッフ募集中!!(動画あり)
●2024.02.03
相馬自動車商工では整備スタッフを募集しております。
整備士の資格はなくてもOK。
資格取得を全面的にバックアップさせていただきます。
車が好きな方のお問い合わせをお待ちしております。
会社見学だけでも歓迎しますよ。お気軽にお問い合わせください。
工場を徘徊して集めた整備ネタをご紹介
●2024.02.03
福祉車両の修理で避けて通れないこと。その5
●2023.08.19
福祉車両の修理で避けて通れないこと。
●2023.07.21
フィアット500Sクラッチ交換
●2023.07.18
先進安全車のカメラ機能調整など
●2023.06.03
工場を徘徊して拾った修理ネタをご紹介。
●2023.04.16